法定相続人
CFPの知識として、相続税の計算にも出てくる法定相続人とは誰を指すのかをしっかり理解して起きましょう。
相続税の計算が、頻繁にCFP試験にも出題されますので、問題を正しく解くためにも正確に覚えておきましょう。
肝心の相続人の範囲ですが、これは民法で決められています。
死亡した人の配偶者は常に相続人になります。
しかし、ここは注意が必要ですが、内縁関係の場合は相続人に含まれません。
配偶者以外の人は、下記の順で相続人となります。
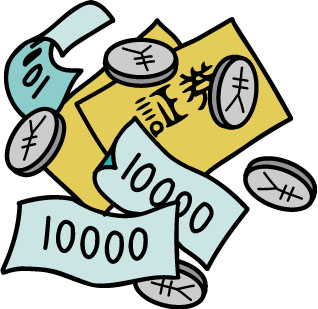
第1順位
死亡した人の子ども。さらに、既にその子どもが死亡しているような場合は、死亡したその子の子どもや、孫などの直系尊属が相続人となります。
子どもと孫と両方が生きている場合は、もちろん子どもの方を優先します。
第2順位
死亡した人の父母や、祖父母などの直系尊属が相続人となります。父母も祖父母が生きている場合は、父母を優先します。
第1順位の人がいない場合に限り、第2順位の人が相続人になることになります。
第3順位
死亡した人の、兄弟姉妹。さらに、その兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子どもが相続人ということになります。
第1順位、第2順位の人がいない場合、第3順位の人が相続人になることになります。
また、相続を放棄した人は当然ですが、最初から相続人でなかったものとみなされます。
しかし、ここが注意点ですが、相続税の控除では、法定相続人として計算式に入れることになりますので注意が必要です。
例をあげますと、亡くなった人に配偶者と子ども2人、亡くなった人の両親、さらに兄弟がいた場合は、民法の規定では配偶者と子どもに相続権があります。
ですから、相続税の基礎控除の計算式は
5,000万円+1,000万円x3(配偶者と子ども2人)=8,000万円という計算になるのです。
つまり、相続した資産が8,000万円までなら、基礎控除額内ですので、相続税を支払う必要は無いということになります。
しかし、この計算はあくまでも民法での規定なので、実際はこの通りに相続しなければいけないということではありません。
控除計算は、試験では特に必要となる知識ですので、十分に覚えておきましょう。
CFPになるための覚える範囲は広いですが、逆を言えば、それだけ多くの専門知識を必要とする価値ある、有益な資格と言えますので、頑張って勉強してくださいね。